漆の美しさと心地よさを再び現代の食卓に。

ごく自然に口から出てきてしまった「うつくしい」という言葉。「きれい」でも「素敵」でもなく、「うつくしい」という形容。「素晴らしい」ですら役不足に思えます。
「美しいですね」。開催中の『いちねんのはじまり展』に並ぶ小林慎二さんの漆の作品を前に、何度もその言葉が使われているのを聞きました。
ふと考えてみると、わたしたちが毎日接するものの中で、そんな風に表現されるものがそれほど沢山あったでしょうか。改めて棚に並ぶ様々な色、形の漆をひとつひとつ見てみても、やはり美しいという表現が一番しっくりと来るのです。それ以外の言葉は浮かんでこないほど。
それは漆そのものの美しさ、なのでしょうか。

9000年という想像もつかないほど遠い昔から、人類が「塗料」や「接着剤」として用いてきたという漆。今現在、これほど発達したと思われる技術をもってしても、漆を超えられる塗料は生まれていないのだといいます。いったい漆のどこがそれほどまでに秀でているのでしょうか。堅牢性、耐久性、耐熱性、安全性。そして、他のどんな塗料にも生み出すことのできない、たとえようのない美しさと優しい手触り。本物の漆のお碗に口をつけたことのある人であれば、その吸い付くようなしっとりとした質感に、心地よさを感じないはずがありません。軽さや、熱々のものでも手が熱くならない実利的な特徴はもちろん、あの官能的な触感は他の素材にはない漆特有のものだと思います。
少し前まで漆は生活のあらゆるシーンで使われていました。建具や家具などは言うに及ばず、楽器や装身具、戦国時代の甲冑となると古い話ですが、漁業で使われる浮きもその一例です。缶詰の内部をコーティングしていた素材も漆だったそう。熱や湿気、酸、アルカリにも強い漆は腐敗防止や防虫の効果もあるため、食品に直接触れる容器や家具に最適だったのですね。
そんなにも優れた漆が、ではなぜ急激にすたれてしまったかと言うと、ひとえに”高価”であることが最大の原因です。安価な合成塗料の台頭で、わたしたちの生活から次々と漆製品が姿を消していってしまいました。家庭でも、ほんの数十年前までは一般の家庭でもお箸やお椀などは塗りのものが使われていたはずです。

ろばの家で初めにご紹介した小林さんの作品はコーヒーカップでした。漆離れが進む中「お椀やお重だとハードルが高くてもコーヒーカップであれば毎日使うものとして気軽に漆の良さに触れてもらえる」という思いで作られたもので、実際、小林さんの漆を見に来てくださる方の中には「あのカップがマイファースト漆です」という方が沢山いらっしゃいます。

こうして漆の良さを実感した方が次に見てくださるのは、はやり圧倒的にお椀、特に汁椀です。毎日飲むお味噌汁。手に持って熱くなく、冷めにくく、口をつけるとしっとり心地よい、そのうえ盛りつけた姿はこの上なく美しいのです。毎朝、毎晩、飯椀と同じくらい頻繁に使うお椀くらい、良いものを使いたい。そう考える人がなんとなく増えているように感じます。もしかすると、家にいる時間が長くなったコロナ渦という状況も影響しているのかもしれません。
万が一割れたり剥げたりしてしまっても繕ってもらえる漆のうつわは、一生、ともすれば子の代、孫の代まで半永久的に使える息の長いうつわ。サスティナブルでもあり、今の世の中だからこそ真価を認めてもらえるものでもあります。
ご結婚祝いや成人のお祝いに。ご出産祝いに、は一般的ですが母となる娘に、離乳食用にと自分が子供のころから使っていたお椀を塗り直してもらったなどと聞くと、漆を使うということを日常の習慣として子供に伝えてゆくことは日本人として、またひとりの親としてひとつの使命であるようにさえ感じてしまいます。
そんな風に長く使ってゆきたいお椀。小林さんが作るお椀はどれも非常にシンプルで流行りすたれに影響されないスタンダードな形のものばかりです。毎日使うものだから使い勝手が第一。普遍的でスッキリした飽きのこない形がいい。「アノニマス」という言葉がありますが、小林さんの漆のお椀を見ていつも思うのはこの匿名性、なのです。
実際に小林さんご自身にお話しを聞いても「この漆はだれだれの作品で…と、ありがたがられるようなのじゃなくていいんです。」と言うのです。「誰のかわからないような、サインもされてないような。その程度の扱いでいいんです。ただ使いやすいなって思ってもらえたらもう十分すぎるくらいです。」

その小林さんは、師匠である輪島の赤木明登さんのもとから独立して今年でもう15年。
「最近やっと、自分の漆が美しいなと思えるようになったんです。」そう静かに、けれどしっかり噛みしめるように小林さんが言いました。
展示二日目の日曜日、小林さんは一日在廊してくださいました。久しぶりにご一緒したお酒の席でのことでした。あまりご自身の仕事を褒めるようなことがなかったので正直驚いたのですが、作品自体がそれを裏付けてなお有り余るほどの説得力を持っていたためか、その言葉は自然に、その場に舞っていた塵が静かに落ち着くような感じで心の中にそっと刻まれてゆきました。となりで一緒に聞いていたパパろばも同じように受け止めているのがなんとなくわかりました。きっとわたしたち二人ともがすでに、作品だけからなにかしら自然と感じとっていたことだったのです。小林さんの言葉がそれを裏付けてくれたようなものだったのでしょう。
「ああ、こうやってただ作ってあげればいいんだ。漆が、塗っている瞬間から本当に美しい。僕はそれをただ、そのままに出してあげればいいんだ。」
そう感じられるようになったのは、ごく最近のことなのだそうです。自分は不器用で、なんでこんなに下手なんだろうとがっかりすることの連続でしかなかったというのです。

下手だなんて思ったことは一度もありませんでしたが、確かにとある瞬間から、納品された小林さんの漆が寒気がするほど美しいと思った頃がありました。もしかすると、それは小林さんご自身が自分の漆を美しいと思いはじめた時期と重なっていたのかもしれません。
「何かが特別変わったわけではないんです。ただ、ひとつひとつの工程、作業をしていて納得のゆく仕事ができるようにはなった、とは言えるかもしれません。」
仕上げの上塗りまで、気の遠くなるような長い工程を踏まなければならない漆の仕事。無数の工程を重ねてゆく中、最終的には目に見えない下地の処理一つをとっても、すべてが気の抜けない真剣勝負の連続です。独立してからの15年間、小林さんは一体何度、同じ工程を繰り返してきたのでしょうか。何百、何千、何万回。ルーティンになってしまいがちな同じ作業の繰り返しの中、ひたすら技を磨き、無駄を省き、さらに奇麗に、さらに丁寧にと精進し続けること。おそらくその作業に没頭している最中には「美しく」とは意識していないのではないでしょうか。
やるべきことをまっとうすること。常に気を抜かず、なまけないこと。どこかで手を抜いてしまえば、どんなに上から漆を重ねて塗りつぶしてもきっと、最後にはにじみ出てきてしまう。微細なひとつひとつの選択の積み重ねが、自然とにじみ出るような「美しさ」を生み出すのではないでしょうか。
わたしたちは、こうして目の前に並ぶ小林さんの作品を手にしてその美しさに素直に感動してしまいます。そして、その美しさを暮らしの中に取り入れることの素晴らしさを、豊かさを、ひとりでも多くの方に伝えたいと心から感じるのです。
はじめて手にするならばぜひ、こんな風に作られた本物の漆を選んで欲しい。自然と「美しい」という気持ちが湧いてきてしまうような、そんな漆。その漆のうつわでいただく一口は、どれほど美味しく感じられるでしょうか。その漆がある食卓は、どれほど豊かに感じられるでしょうか。自然と、背筋が伸びます。お椀の上げ下げにも、自然と手を持ち替えます。ごく自然に、所作まで美しく導かれるのです。その連鎖は、なんて美しいことなんだろう。
出展されたすべての作品を掲載することはできませんでしたが、あたらしくはじまる一年を迎えるのにぜひ使ってみていただきたい、そんな作品から優先して掲載するよう心掛けました。
漆の素晴らしさ、そして小林さんの漆の、背筋の伸びるような美しさまでお届けできますように。
小林さんの作品はこちらのページから。
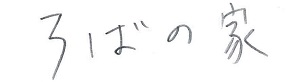




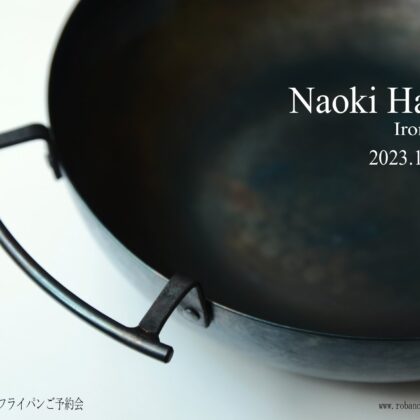
 お問い合わせはメールでお願いいたします。SNS等のDMによるお問い合わせには対応しておりません。ご了承ください。
お問い合わせはメールでお願いいたします。SNS等のDMによるお問い合わせには対応しておりません。ご了承ください。



